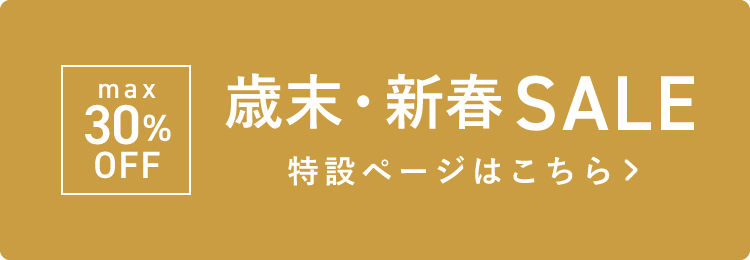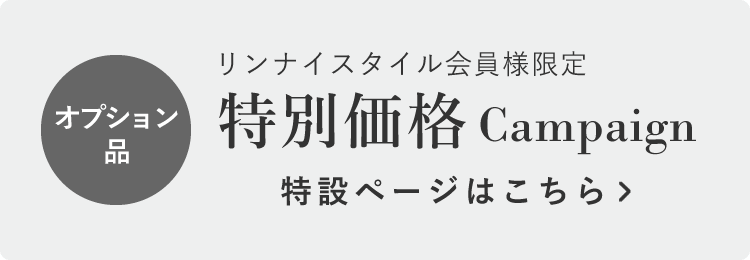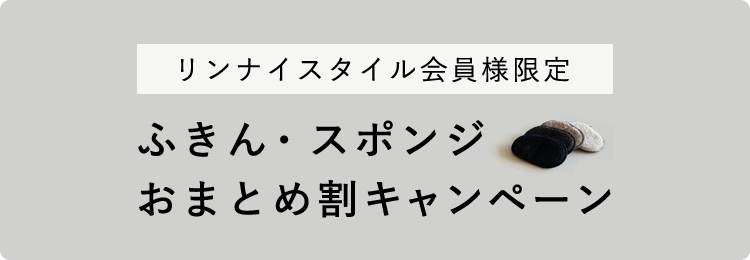掃除がラクになる、掃除の基本をおさらい。

出典:写真AC
日々のお掃除で、新しい汚れや落としにくい汚れに出会う度に掃除方法に困っていませんか?
今回は掃除のプロの大津たまみ先生に、これさえ知っていれば大抵の汚れは落とせるようになるという「掃除の基本」を教わります。
世の中に存在する様々な掃除テクニックや道具、洗剤も、この基本がわかれば迷わずに使いこなせ、ラクに効率的に掃除ができるようになります。
掃除の基本―4つのポイント
- 掃除の「四要素」を活用する。
- 汚れに合った洗剤を使う。
- 掃除道具を正しく使う。
- 汚れをためない掃除習慣を作る。
掃除のプロが伝授する「掃除の基本」は一生使える知識です。
ぜひ身に着けてご活用ください。
ポイント1:掃除の「四要素」を活用する。
ひとつの汚れを落とす時には「洗剤の濃度・時間・物理力・温度」の4つの要素が作用すると言います。
この中の物理力とは、汚れを落とす際に必要になる力のことです。
こちらはそれを図にしたもの。
大津先生はこれを「掃除の四要素」と呼んでいます。
それぞれの要素の割合を変化させることで、掃除時間が短くなったり、弱い力で汚れを落とせるようになります。

例えば、次のような掃除方法があります。
方法① 強い洗剤を使って強くこする。
特に大掃除でこの方法を使われる方は多いのではないでしょうか。
この時のグラフは、強い洗剤=洗剤濃度を上げる、強くこする=物理力が大きい、となります。この2つの割合が大きくなれば、自然に掃除時間は短くなります。
ただ、強い洗剤を使うと掃除をする場所や健康を損なうことがありますし、力を入れてこすると体に負担がかかります。

そこで、掃除のプロがよく採用するのが次のような方法です。
方法② 洗剤をお湯に溶いてつけ置き洗いをする。
大津先生を始め、掃除のプロがよく行うつけ置きの掃除方法は、この四要素の理論に寄るものです。
お湯を使う=温度を上げる、つけ置きをする=時間をかけるとすると、自然に、洗剤はあまり強くなくてもよくなりますし、力を入れてこすらなくても落ちることになります。

リンナイスタイルコラムでも、ガスコンロのごとくやレンジフードのシロッコファンに付着したガンコな油汚れを、重曹や中性洗剤等を溶かしたお湯に一定時間つけ置きしてからブラシで洗う方法をご紹介してきました。
温度を高めに保つことで一般的な洗剤でもガンコな汚れがゆるみ、力を入れずに汚れを落とせるようになります。

また、カビを除去する際の掃除方法もこれに似ています。
カビ取り剤(高い洗剤濃度)を吹き付け、その上からペーパータオルなどで湿布して洗剤を密着させて時間を置き、ブラシでこすって落とします。
温度を変えることはできませんが、ほかの2つの要素の割合を高くすることで、洗剤が汚れにしみこんで、短時間で弱い力でも落としやすくなります。
このように、四要素を理解しておくと無理のない掃除方法を考えられるようになりますので、ぜひ覚えておいてくださいね。
ポイント2:汚れに合った洗剤を使う。
汚れを適切に落とすために汚れの性質に合う洗剤を選び、正しく使うことは掃除の基本です。
洗剤を選ぶ基準は様々ですが、掃除のプロの中にはエコ洗剤を選択する人が多いそうです。

端にいくほど洗浄能力が高くなります。
洗浄能力が高い洗剤を使う方が早くきれいに汚れを落とせるように思いますが、強い洗剤は掃除する物の表面を傷めたり、人の健康を害したりする可能性があります。
また、強い洗剤や大量の泡が発生する洗剤は掃除後に洗剤が残らないように念入りに洗い流す必要もあるため、かえって時間と手間がかかり、環境にも負担がかかります。
ポイント1の四要素を知っていれば、必ずしも強い洗剤を使う必要がないこともわかります。
大津先生も「最近は環境や健康に配慮しつつ、汚れ落ちの良いエコ洗剤が増えているので、積極的に取り入れています」とのことです。
汚れの性質別、エコ洗剤の使い分け方。
今回は、エコ洗剤の中でも掃除のプロがよく使う、重曹セスキ・炭酸ソーダ・クエン酸の特徴と使い分け方をご紹介します。

重曹:ごく弱いアルカリ性。
キッチンの油汚れ、調味料汚れ、シンクの中等油汚れが混じっていると思われる場所、ドアノブや壁等の手アカ汚れ等、酸性の汚れを落とす。
セスキ炭酸ソーダ:弱アルカリ性の洗剤。
重曹と同じく酸性の汚れを落とすが、重曹よりもアルカリ性が強く、洗浄力も強い。キッチンのガンコな汚れに。
※すべての物に使えるわけではありません。使用前に必ず説明書きを確認してください。
クエン酸:弱酸性の洗剤。
トイレやシンクにこびりついた水アカ、水まわりの白いカルキ汚れなど、アルカリ性の汚れを落とす。

掃除のプロ大津先生が日々使っているのが弱アルカリ性のエコ洗剤「天使の松」です。
原料は米ぬか、ヤシ、松の木の油分。
洗浄能力が高く、洗い流す際の泡切れも良いです。
肌が弱い大津先生とも相性がよく、自然に分解されやすいとのことで、安心して長年公私に渡って使い続けているそうです。
ポイント3:掃除道具を正しく使う。
掃除道具は、正しい使い方をすることで本来の良さが活き、掃除もラクになります。
中でも一般的な、スポンジ・ブラシ類・雑巾(クロス)の正しい使い方をご紹介します。
スポンジ

スポンジは「やわらかい面」と「固い面」の両面がある物を選びましょう。
それぞれ傷つけたくない場所を洗う用、こびりついた汚れをしっかり洗う用と使い分けるのがコツです。
雑巾・クロス

雑巾やクロス を使った拭き掃除では、拭く順番を意識しましょう。
手のひらサイズにたたんだら、奥から手前に向かって、上から下に向かって動かします。
矢印のようなコの字拭きをすると拭き残しがなくなります。
ブラシ類

ブラシやハケのように毛の長い掃除道具は、毛先を立て、汚れに対してできるだけ直角に当てることを意識しましょう。
それがホコリであれヌメリ汚れであれ、汚れが落ちやすくなります。
掃除の後は道具のお手入れを。

どの掃除道具にも共通しますが、 使用後は常に清潔に保つようにしましょう。
掃除が終わったら、仕上げとして使った道具の汚れをしっかり落としてよく乾かします。
道具が汚れたままにして次の掃除をすると、汚れを広げてしまうことにもなります。
こまめな洗浄を行い、時期を見て交換しましょう。
ポイント4:汚れをためない掃除習慣を作る。
最後のポイントは掃除をする習慣について。
汚れがたまる前に掃除する習慣が身につけば掃除はラクになり、いつも気持ち良い空間で暮らせるようになります。
特に次の2点を意識しましょう。
汚れがついたらすぐに落とす。
汚れは時間が経つと固まり、落としにくくなります。早期発見・対応で、掃除が大変になるのを防ぎましょう。
“ついで掃除”を習慣にする。
料理の間にキッチンを拭く、入浴後にお風呂の壁をこする等、ちょっとした掃除を日々の暮らしに取り入れ、こまめに掃除をする習慣にしましょう。
まとまって掃除をするよりも手間と時間を減らせます。
大掃除もずっとラクになります。

掃除の基本を覚えて、負担を軽くしましょう。
新しい汚れに出会う度に掃除方法を調べたり道具や洗剤を用意するのは大変です。
そんな時に、掃除の基本のポイントである4つ、「四要素」の考え方、洗剤の選び方と使い方、道具の使い方、掃除習慣を知っていれば、ラクに汚れを落とせます。家の中のピカピカも維持しやすくなります。
特に「四要素」は、自分で考えて、応用しながら掃除が可能になるので、掃除の負担もぐっと少なくなります。
新しい汚れに出会った時は、基本を思い出して挑戦してみてください。
お掃除が少しでもラクにできるようになるといいですね。