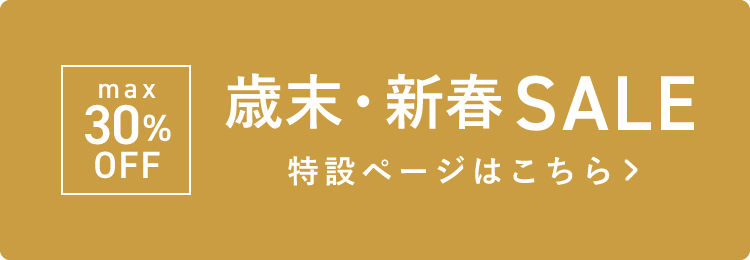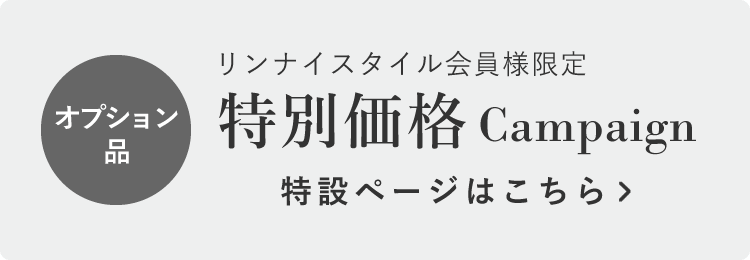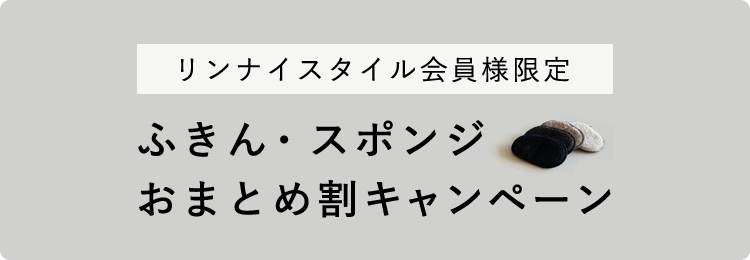掃除のプロが教える「ほうき」と「ちりとり」の選び方・使い方。
「ほうき」と言えば、魔法使いが空を飛ぶ時に使うもの。
いえいえ、それはお話の中のこと。
現実の世界では畳の部屋やベランダ等の外回り、ペットがいるご家庭でもほうきは欠かせません。
気づいた時にサッと手にとってすぐにキレイにできる便利さから、掃除機と使い分けている方も多いようです。
そこで気になるのが使いやすさ。
身近なだけに、使い勝手は重要です。
今回はお掃除と収納のプロ、大津たまみ先生に「ほうき」と「ちりとり」の選び方、使い方を教わります。

掃除のプロの「ほうき」の選び方。

室内用のほうきを選ぶ時は、ほうきの先が縮れているものを選びましょう。
ホコリや小さなゴミを絡め取るので掃除がしやすいです。
素材は“ほうき草”を使ったものが一般的ですが、最近はちょっと高級なシュロを使ったものも人気だそうです。

また、根元がしっかり束ねられているものを選ぶことも大切です。
ここがゆるくなっていると穂が抜け落ちてきたり、ほうきの先が割れたりバラけたりして、使いにくくなってしまうそうです。

もうひとつ重要なのは、柄の長さです。
背筋を伸ばしたまま掃ける、長い柄のものを選んでください。
柄が短いと前かがみの姿勢になり腰に負担がかかります。
掃き寄せる動きも大きくなって、掃除がしづらく、より腰を痛めやすくなります。
掃除のプロが「絶対コレ!」と断言する「ちりとり」。

お掃除のプロが勧めるちりとりは通称「ブンチリ」。
「文化ちりとり」というものです。
持ち手の部分が長く、倒せばフタが自動的に開くので立ったまま作業ができる便利さです。
集めたゴミも散らかりにくく、ゴミを貯めておけるように容量も大きいので、清掃業の現場ではちりとりといえばこの「ブンチリ」というほど定番なのだそうです。
外には外用の「ほうき」と「ちりとり」を。

ベランダや庭など、外で使うほうきはポリエステル等の化学繊維製の物がおすすめです。
泥汚れがついてもすぐに洗えるからです。
ちりとりも、同じように洗える素材のものが良いです。
ベランダ等では写真のようなちりとりが手軽ですが、広い場所の掃除にはやはり「ブンチリ」が使いやすいそうですよ。
あらためて、「ほうき」の使い方をおさらい。

掃くときは畳やフローリングの目に沿ってほうきを動かします。
遠くのゴミやチリを引きずるようにして掃き寄せる方もいますが、それはあまりおすすめできません。
ほうきを動かす距離を短くして、自分が動きながら掃き寄せるようにすると、ホコリやチリが舞い上がらず、効率よく掃除ができます。
集めたゴミをちりとりに入れるときは、ほうきの柄を腕に絡ませるようにして腕で動かすと、こぼさずにちりとりにしっかり入れられるそうです。
ほうき掃除をする時にちょっと意識してみてくださいね。
しまい方次第で使いやすさは長続き。

ほうきを
立てかけて収納してしまうと、ほうきの重みで穂先が曲がってしまい、掃きづらくなります。
気付いた時にすぐに使えるような場所に収めるのも大切。
最近のほうきはおしゃれなものも多いので、あえて室内に吊るしてインテリアにされている方もいらっしゃるそうです。
あなたが知らない「ほうき」の世界!?
最後に、身近な掃除道具のほうきですが、何万円もする物もあることをご存知ですか?
国産の素材を使い、職人がひとつひとつ手作りをしたほうきは、高価な分掃き心地もケタ違いだとか。
最近はいい物を長く使いたいという理由から、そんな高級ほうきを選ぶ方が増えているのだそうです。
どんなほうきか気になったので、大津先生がお持ちの高級ほうきを見せていただきました。

大津先生のお気に入りは、小ぶりながらも職人が手作業で仕上げた逸品。
デザインがおしゃれなので外に出しておけて、気になった時に手に取って掃除がしやすいのだそうです。
柄が持ちやすく上から力が入れやすいので、はば木やサッシ等細い場所のホコリ取りに大活躍。

サッシを軽くなぞっただけでこんなに汚れが!
毛の固さがほどよいので、こびりついている汚れも取りやすいそうです。
束ねている根本部分は、手作業で糸できっちり縛り上げられているのが分かります。
ちなみに…お値段はヒミツとのことでした。
広い場所から細かな場所まで活躍するほうき。もう一度見直して、生活に取り入れてみませんか?